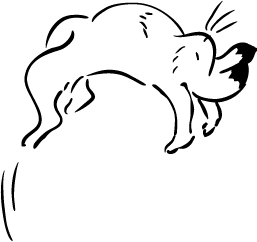第53回(令和3年度)試験「受験案内」がアップされた!
いよいよ受験案内が発表された!
こんにちは。
社労士試験を平成30年に合格し、今は社労士受験生と、労務ワーカーを応援するブログをしている11ぴきのぺんぎんです。
さて、いよいよ社会保険労務士試験オフィシャルサイトに第53回(令和3年度)試験受験案内がアップされました!

受験案内のPDFはこちらです。
令和3年は大きくレイアウトが変わっている!
目次がある!よくある質問がある!見やすい~(^^)
さて、今回は、はじめて受験される方向けに、受験申込までの流れと、自分が申込時に注意していた点、そして令和3年度の変更点についてまとめてみたいと思います。
複数回受験の方で、「変更点だけ知りたい!」という方は、資格の大原のカリスマ先生こと、金沢先生が解説してくださっているので、そちらをチェックです!

相変わらず、わかりやすい~!!
もちろん私のブログも読んでもらえたら嬉しいですが、受験生にとって時間は命ですから(^^;)
本試験・合格発表の日程
さて、まずは肝心な試験日と、合格発表の日にちから確認してみます。
試験日は、令和3年8月22日(日)、合格発表日は令和3年10月29日(金)です。
この日程を見ているだけでも、私まで身が引き締まる…(゚Д゚;)
そして、今までは11月の合格発表だったのが、10月になっている!
本試験から合格発表までは、合格基準点がはっきりしない、受験生にとってはしんどい時間なので、その時間が少しでも短くなったのは嬉しい…!
今年の10月、たくさんの桜が咲きますように…。
試験当日の時間
そして、続いては、試験当日の日程です。
- 10:30~11:50 選択式(80分)
- 13:20~16:50 択一式(210分)
と、こちらは昨年と変わらないスケジュールです。
それでは、令和3年10月29日に、最高の日を迎えるために、まずは受験申込!ということで、今回は受験申込の簡単な流れをまとめてみたいと思います。
受験申込までの簡単な流れ
受験案内等必要な書類を郵送で請求する ※令和3年は郵送のみ!
まずは受験申込のために必要な資料を入手する必要があります。
受験案内のほかに受験申込書等が必要となりますが、それはインターネットでもダウンロードできず、窓口で受け取ることもできないので、必ず郵送で請求する必要があります。(電話・FAX による請求もできません)
※以前は、試験センターまたは都道府県社会保険労務士会の窓口で受け取ることができましたが、令和3年は郵送での請求のみとなりますのでご注意ください。
請求方法については、社会保険労務士試験オフィシャルサイトに掲載されています。
請求期間は、令和3年3月1日~5月31日となっていますが、書類の返送の関係上5月14日までの請求が推奨されています。
まだ請求していない方は、まずはお早めに請求しましょう(^^)
・令和3年の試験の請求方法はこちらです。
郵送で請求した場合、書類の返送は、試験センターに到着した2営業日後を目安に発送されるそうです。
試験申込締切日(5 月 31 日)前後に到着したものについても発送されるそうですが、試験申込みに間に合わない場合の責任は負いませんとしっかり明記されていますので、やっぱり早めに請求したほうがいいですね…。
受験資格の確認をしておく
受験したい!と思っても、そもそも受験資格がない場合は受験できなくなってしまうので、まずは受験資格があるのか、そのために必要な書類は何か確認しておきましょう。
直近3年間で社労士試験を受験した場合
まず、過去3年の社労士試験を受験している場合は、そのときの試験の受験票もしくは成績(結果)通知書の原本を持っている場合は、それを受験資格証明として提出できます。
私は2年目からは、成績(結果)通知書は手元に残しておきたかったので、前年の試験の受験票の原本を受験申込の際に提出していました。
初めて受験する場合
始めて受験する場合は、受験資格が必要です。
社労士を受験するための受験資格については、社労士試験公式サイトの受験資格のページにで確認できます。

受験資格の条件はいろいろなものが用意されていますが、大きく分類すると、
1.学歴、2.実務経験、3.試験合格
の3つに分けられます。
少し簡単に3つのパターンの一例と必要な書類を紹介します。
1.学歴の一例…
大学・短大・高専(5年制)を卒業した人
→卒業証明書または卒業証書の写し、学位記の写し
2.実務経験の一例…
労働社会諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になるもの
→事業者またはこれに代わるべきものが当該従事期間を証明する書面
3.資格合格の一例
…行政書士となる資格を有するもの
→合格証書等
と、こんな感じです。
私の場合は、実務経験が3年以上あったので、会社で証明を書いてもらうことにしました。
ただ、会社の複数の人に受験することが知られないよう、当時の上司である人事部長が証明を作成くれたので、ほかの人には知られることなく、受験することができました。
会社に書いてもらう場合、どんな内容で書いてもらえればいいか、様式と記入見本がこちらも社労士試験公式サイトにあります。
実務経験証明書の様式と記入例はこちら。

この実務経験証明書は、受験案内に同封されてきますのでご安心を。
ただ、もし会社には知られたくないという場合で、学歴要件を満たしているのであれば、学歴の証明書を提出しておけばOKです。
私はそのあたりがよくわかっておらず、受験の際に実務経験を証明しておけば、合格のときに実務証明は不要なんだと勘違いして「実務経験の証明で出さねば!」と勘違いしていました。(-_-;)
社労士合格後に、社労士登録する場合は、改めて労働社会諸法令の実施事務に2年以上あるという会社の証明提出するか事務指定講習の受講が必要になります。
なので、どっちみち会社に証明をもらうのであれば、合格してからでもいいかと思います。
証明書類の注意事項
証明の氏名と現在の氏名が異なる場合
証明の氏名と現在の氏名が異なる場合は、改正した事実を証明する個人事項証明(戸籍抄本)の添付が必要となりますのでご注意を!
また、戸籍抄本は、申し込み前3か月以内のもので、原本であることが必要になりますので、そちらもあわせてご注意ください。
受験案内が届いたら
それでは次に、いよいよ受験案内が自宅に届いたの後の説明に入ります。
私はいつも郵送で請求していたので、4月の中旬になると、請求の際に自分で同封した返信用封筒で届くので、きたきた!となりました。
受験案内の内容を確認する
まずは、受験案内の封筒に、以下の5点が入っているか、しっかり確認しましょう。
- 受験案内
- 受験申込書(OCRシート)
- 受験料払い込み用紙
- 実務経験証明書
- 受験申込用封筒
受験申込の受付期間をチェック!
次に、なにはなくとも、受験申込受付期間の確認をしておきましょう。
令和3年度の社労士試験の申込期間は、
令和3年4月19日(月)から令和3年5月31日まで ※5月31日の消印有効
となっています。
※新型コロナウイルスの影響で令3年については、窓口受付はおこなっておらず、郵送のみとなっておりますのでご注意ください。
私は毎年できるだけ早く、遅くともゴールデンウィーク前には郵送することを心がけていました。
試験地・試験会場の確認 ※令和3年変更あり
令和3年の社労士試験で最も大きい変更点の一つとして、当日の本試験を受ける試験地のみを希望・選択するだけで、試験会場の希望が出せないという点です。
令和2年までは、社労士試験の試験会場の割当は、申し込みの順番でした。
つまりは、希望していた会場が定員に達した場合は、別の会場に割り当てられてしまうということもありましたが、比較的早めに申し込んだ場合、自分の希望する試験会場になることが多かったように思います。
私は地方住まいなのですが、新幹線が東京までつながっているので、毎回試験地の希望は東京都の日本大学法学部にしていました。
合計4回受験しましたが、どの時も最寄りは水道橋駅の日本大学のキャンパスで受験できました。
しかし、令和3年からは、希望する都道府県(試験地)をのみを希望・選択するのみに変わっています。
試験地については、全国の中でも、エリアごとに合計19都道府県の中から選ぶことになります。
試験地は、
北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県です。
しかし、試験地を含め、実際どの試験会場になるかは、受験票(8月上旬に届く予定)が届くまでわかりません。
受験案内にも、試験会場に関する照会には応じることができないことがはっきり明記されています。
直前までは試験会場の予測がつかないことは、今までと比べて不安材料と感じる人も多いかもしれません。
でも、それはきっとほかの受験生のみなさんも同じはずです。
このコロナ禍において、生活の中でもたくさんのイレギュラーな対応をしなければならないことについて、みなさんも日常の中で必死に対応されてきたのではないでしょうか。
そんな日々を乗り越えて、勉強を続けているみなさんなら、きっと今回も、乗り越えられると、私は勝手に思っています。
それぐらい、このコロナ禍で、社労士の勉強を続けているみなさんは、本当にすごいです!!
ただし、どんな対応になるかわからないからこそ、早めに申し込んでおいたほうが安心できるということには、変わりはないのではないでしょうか。
受験申込書に貼る証明写真を撮る
次に、受験申込書に貼付する証明写真を撮りましょう。
この写真は、縦45mm、横35mmで、「申し込み前3か月以内に撮影したもの」となっています。
また、試験をうけるときに眼鏡をしている人は、眼鏡を着用して写真を撮ることをお忘れなく。
本試験当日は、この写真と席に座っている本人を見比べて、試験官が本人確認していきます。
こちらの写真は、本試験のみで使用するだけで、その後の登録等に利用したりはしないので、そんなに気合いをいれた写りにしなくても大丈夫です(^^;)
コンビニまたは郵便局で受験料を振込む ※令和3年変更あり
次に受験料を振り込みましょう。
振り込みは受験案内についていた、専用の払い込み用紙でコンビニまたは郵便局で支払います。
ここで、2つ目の令和3年の大きな変更点があります。
受験料が、値上がりしています…。
これは以前発表されたときにも、Twitterを騒がせていましたが、こればかりは、受験生の努力ではどうしよもないですもんね…。
受験料は15,000円+手数料203円の合計15,203円です。
コンビニの場合は「払込受領書」の原本、郵便局の場合は、「振替払込受付証明書(お客様用)」の原本を受験申込書と一緒に送付する必要がありますので、なくさないようにご注意を!
私は毎年最寄りのセブンイレブンで振り込んでいました。
コンビニで振り込むと、「払込受領書」と「振替払込受付証明書(お客様用)」の両方をくれるため、「振替払込受付証明書(お客様用)」は手元にのこしてあります。
受験申込書を記入する
次に受験申込書を記入しましょう。
受験申込書は、厚紙でA4サイズです。OCRで読み取るので、記入は黒のボールペンではっきりと書きます。
申込書に貼り付ける写真の裏面には、「住所・氏名」の記入を忘れずに!
受験資格を証明する書類を準備する
さきほどの、「受験資格を確認しておく」のところで説明したものを用意します。
簡易書留郵便で郵送
ここまできたらあとちょっと!
あとは必要書類をそろえて、専用の緑色の封筒にいれて、郵便局窓口から簡易書留で送付するだけです。
受験申込書は簡易書留で送ることが必須ですので、間違ってもポストに投函してはダメです!!
簡易書留で送ると、窓口で「書留・特定記録郵便物等受領証」というレシートがもらえます。
そこには依頼主の住所氏名と、届け先の名前、追跡用の問い合わせ番号が記載されていますので、8月上旬に受験票が届くまでは大切に保管しておきましょう。
なお、受験票が8月10日(火)までに届かない場合は、8月12日(木)までに試験センターまで連絡をしてくださいとの記載があります。
まだまだ先のお話ですが(^^;)
以上が、ざっくりした受験申込までの流れです。
いろいろと心が落ち着かない日々ではありますが、合格目指して努力を続けるみなさんに、私もたくさん勇気をもらっています。
本当にありがとうございます。
これからも、微力ながら応援しています!
まとめ
- 受験申込のために、まずは受験案内の請求を郵送でしよう!
- 令和3年度は、新型コロナの影響ですべて郵送のみなので注意!!
- 書類が届いたら中身を確認して、受験案内をよく読もう
- 会社に内緒で受験したければ、受験資格は学歴要件でクリアできればベター
- 送付するときは簡易書留で!